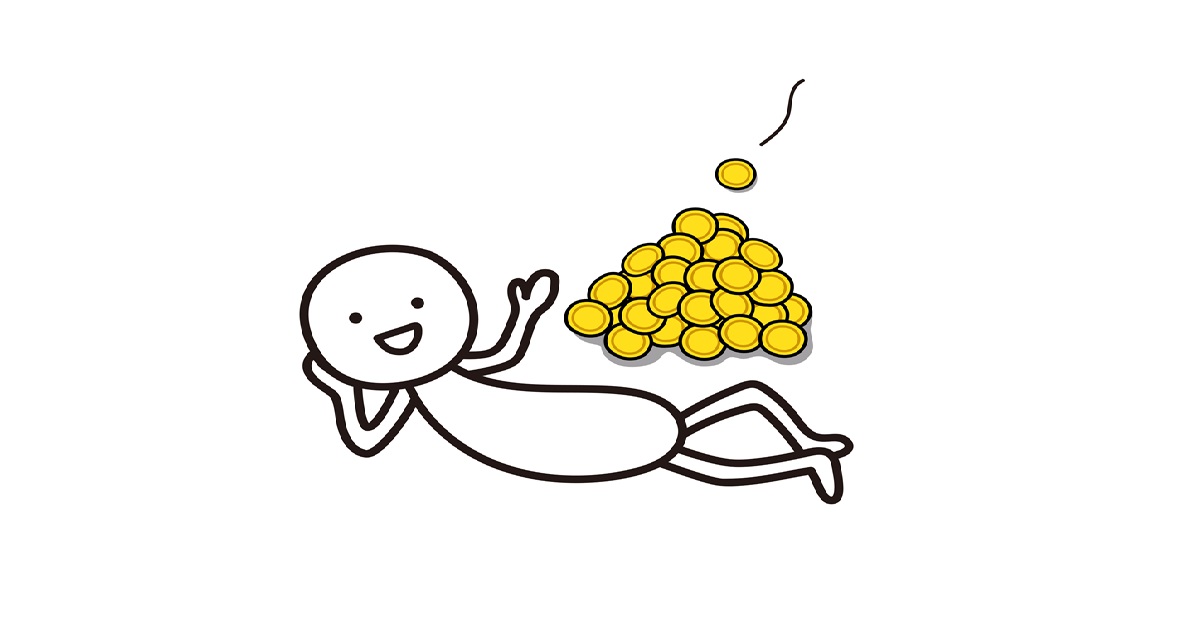心と体を壊し、社会から脱落したか。
だが、それは終わりではない。
お前がこれまで律儀に払い続けてきた社会保険料を、利息付きで回収する時が来ただけだ。
これから授けるのは、会社を辞めた後も最長1年6ヶ月間、給料の約3分の2を国から引き出し続ける「傷病手当金」という名の「合法的延命装置」を起動させるための、禁断の裏ワザだ。
【絶対条件】延命装置を起動させるための「2つの鍵」
この装置を起動させるには、2つの「鍵」が必要だ。
一つでも欠けば、お前はただの無職に成り下がる。
鍵①:社会保険の加入期間が「継続して1年以上」あること。
在籍期間ではない。
休職中であろうと、社会保険に1年以上ぶら下がっていたという事実が、お前にこの権利を与える。
鍵②:退職日に、絶対に出勤しないこと。
これが、凡人がハマる最大の「罠」だ。
挨拶ごときで会社に顔を出した瞬間、お前は「働ける人間」だと見なされ、全ての権利を剥奪される。
退職日は有給を使い、社会から完全に姿を消せ。
【レッドゾーン】受給中に副業で稼ぐ「沈黙の掟」
傷病手当金は、あくまで「働けない」人間のための制度だ。
だが、その金だけでは生きていけないのが現実だろう。
ならば、制度の監視網をくぐり抜け、「沈黙のまま」稼ぐしかない。
バレれば、不正受給として地獄を見ることになる。
その覚悟がある者だけ、以下の境界線を知れ。
- 社会保険に紐づかない仕事(業務委託、アンケートサイトなど)
- 給与明細が出ない仕事(メルカリでの不用品売買など)
- 労働と見なされない所得(株の利益など)
そして、最も重要な掟は「誰にも話すな」。
制度の監視より恐ろしいのは、お前の成功に嫉妬する、友人や同僚からの「密告」だ。
お前は、孤独な戦場にいることを忘れるな。
【最強コンボ】傷病手当金 → 失業保険へ繋ぐ裏コマンド
1年半の延命期間が終了しても、まだゲームは終わらない。
ここから「失業保険」へと繋ぐ、最強のコンボが存在する。
傷病手当金をもらい始めたら、即座にハローワークへ赴き、「受給期間の延長手続き」を行え。
この一手間を怠った愚か者は、傷病手当金が切れた瞬間、何のセーフティーネットもない荒野に放り出されることになる。
この「裏コマンド」を入力した者だけが、さらなる延命期間を手にする資格を得るのだ。
【思考の武器】孤独な戦いを乗り切るための精神武装
この1年半は、社会から断絶された、孤独な戦いだ。
精神を病めば、お前は二度と社会復帰できなくなる。
そうなる前に、お前の腐りかけた精神を、偉人の言葉で武装しろ。
絶望の淵でこそ、人間の真価は問われる。
この一冊が、お前の思考を鍛え、次なる戦いへと備えさせる。
あわせて読みたい
傷病手当金という延命装置を使い切った後、お前が次に狙うべきは何か。
それは、うつ病ですら受給可能な「障害年金」という、本当の意味での最終手段だ。
以下の記事で、その審査を突破するための禁断の裏ワザを解説している。
この記事について
このブログの情報には、読者からの情報買取によって成り立っている記事も含まれる。
そのため、記事内容の正確性や安全性は一切保証しない。
ここに書かれた知識の悪用は固く禁ずる。
万が一、お前が何らかの行動を起こし、いかなる損害を被ろうと、それは100%お前の自己責任である。
案件ブログが、お前に救いの手を差し伸べることは未来永劫ない。
.png)